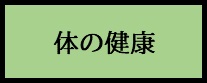自分は医師から高血圧と診断されました。
高血圧を下げることにはどうすべきかを考えてみました。
なお、自分としては次の習慣があります。
① 一日二食を50年以上続けています。
② 食事時間は不規則ですが、近頃は身心の疲れが取れるように8時間以上は寝るようにしています。③ 酒は飲まないし、タバコも吸いません。
④ 健康食品やサプリメントも使っていません。
1. 血圧とは何か
先ず、心臓は、収縮・拡張を繰り返して、血液を動脈に送り出しています。
血圧は、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す圧力をさします。血管が血液を送り出すときの血圧が収縮期血圧です。逆に、心臓に血液が送り込まれて拡張した時の血圧が拡張期血圧です。
血圧測定器で測りますと、収縮期血圧が最高血圧となり、拡張期血圧が最低血圧となります。
この血圧は、診察室での計測値の方が自宅で測るより少し高いそうです。心理的なものと思われます。
診察室での血圧の正常値は、最高血圧が139mmHg以下、最低血圧が89mmHg以下と云われています。
自宅での血圧の正常値は、最高血圧が134mmHg以下、最低血圧が84mmHg以下と云われています。
血圧の測定は、腕や手首に巻いたマンシェットという「ゴム袋が入った細長い布」を膨らませることで測定します。測定された血圧は、最高血圧と最低血圧の2つの数値で表されます。
2. 血圧の変動要因
血圧は、自律神経の調節状況によって変動します。それは、時間帯、行動、環境など様々な要因によって変動します。
2.1. 血圧を上げる要因
・ 睡眠:睡眠不足がある
・ 精神:不安・緊張・疲労などのストレス、何かの物事に集中する
・ 運動:歩く、走る、スポーツなどの運動をする
・ 飲食:料理する、食事する
・ 塩分:塩分を摂りすぎる
・ 禁煙:たばこを吸う
・ 入浴:入浴する
・ 気候:寒い・暑い、気圧変化、天候変化が激しい
・ 性別:男性の血圧は女性よりも5~10mmHg高いそうです
2.2. 血圧の日内変動
血圧の日内変動とは、一日の中で一定の変動があります。
朝起床して活動量が増える日中は血圧が上がり、活動量が減る夕方から血圧が下がり、睡眠中はさらに低くなります。
2.3. 血圧の季節変動
血圧の季節変動は日内変動と似た変動があります。
春から夏の気温が上昇している季節には血圧は下がり、秋から冬にかけて気温が低下する季節には血圧は上昇します。
2.4. 血圧を下げる要因
血圧を下げるものとしては、安心・安静・深呼吸・排尿・排便・特定な食事摂取などがあります。
3. 高血圧を下げる方法
3.1. 料理する食材の変更
①. 減らす食材
これは、塩分(塩化ナトリウム)を多く含んだ食べ物を減らすことです。
塩分を過剰に摂取しますと、塩分のナトリウムが血液の浸透圧を一定に保つため、必要な水分が増え、体内を循環する血液量を増やすそうです。
すると、血液の量が増えますと、血管の壁を押す圧力が高くなり、血圧が高くなります。
塩分を多く含む食材として、味噌・醤油など調味料、漬物、ラーメン・カップ麺など多くの保存食品に含まれています。これらの食品を過剰に摂取しないように減らすことが大切です。
②. 増やす食材
血圧を下げるために塩分を減らせにくい場合は、カリウムを多く含んだ食材を多く摂取することです。ナトリウムを排尿してくれます。
尿のナトカリ比(ナトリウム÷カリウムの比率)が低いほど高血圧のリスクが低いそうです。
カリウムを多く含む食材を例示します。
・ 果実類:アボガド、バナナ、キウイ、リンゴ、オレンジ、みかんなど
・ 野菜類:ほうれん草、小松菜、ニンジン、ニラ、大根、トマト、かぼちゃ、なす、芋類、豆類など
・ きのこ類:エリンギ、椎茸など
・ 加工食品:豆腐、納豆、牛乳、ヨーグルト、豆乳など
・ 魚介類:まだい、まぐろ、ぶり、鮭、さわらなど
・ 海藻類:昆布、わかめ、ひじきなど
・ 肉類:豚ヒレ、牛ヒレ、鳥のささみなど
3.2. ストレッチ
血液を流れやすくするために行います。
① 体を曲げるストレッチ
・ 首を左にゆっくり曲げ、その状態を保ち、ゆっくりと首を起します。順次右、後、前と曲げていきます。
・ 仰向けに寝て、足を伸ばします。片方の足の膝を出来るだけ胸に近づけるように曲げ、その状態を保ち、ゆっくりと足を戻します。次に反対の膝も行います。
② 肺の筋肉のやわらげ
心臓は、肺の筋肉に護られています。その筋肉を和らげます。
座って、姿勢を正し、出来るだけ肩だけを後ろ引き、その状態を保ち、肩を正常に戻します。
3.3. 足のツボ
足には高血圧を下げるツボがあります。
・ 足の裏には、腎系のツボ(腎臓、尿管、膀胱)、肝臓と心臓のツボがあります。
・ 足の甲には、リンパ腺系のツボがあります。
・ これらのツボを押すか、もみます。
4. 参考資料
快眠、快食、快運、快水、快便の五快については、次の図をクリックして下さい。